29日、衆院テロ防止特別委員会で開かれた守屋前防衛事務次官の証人喚問の中継を移動中の車内で見ました。
自民党の質問者が次の故事を引用し、「そんなことでは困る・・・」という調子で謝罪を求めていました。
「瓜田(かでん)に履(くつ)を納(い)れず、李下(りか)に冠(かんむり)を正さず。」
「李下に冠を正さず」という故事はこの問題に対してちらほら見られる言葉ですが、正直その意味は・・・(^_^;)
調べてみると・・・ちょっと違和感を感じました。
出典の現代語訳は以下のようにされていました。
「君子たるものは、人から疑いを招くような事を未然に防ぎ、嫌疑をかけられるような振る舞いはしないものだ。(取ろうとしていると勘違いされぬように)瓜(うり)畑の中で靴を穿(は)くような仕草をしたり、李(すもも)の木の下で冠をかぶりなおしたりはしないものだ。」
この故事が示している「嫌疑をかけられるような振る舞いはしないものだ」というコンセプトはこのような問題の再発の予防にはつながりません。この故事をあのような場で引用するセンスも、このような問題が起こる温床だと思います。
以前このサイトの「膿みを出すとは」に書きましたが、「膿み」は出すだけではだめなのです。
例えば背中にできたアテローム(粉瘤)が化膿してしまい、膿がでるようになった場合外科では以下のように処置されます。
(問題の重大さからすると、指先がちょっと膿んだという程度ではないでしょう)
・局所麻酔下で行います(麻酔なしでは無理です)。
・切開は十字に入れます。アテロームの大きさに対して充分切ります。
・膿を搾り出すだけではありません。膿を包んでいた袋の残骸もろともスプーンのようなもので掻きだします。つまり”新しい組織が露出するまで古いものを取り除く”わけです(結構血が出ます・・・)。
・切開創は縫いません。膿で汚染した傷は閉じません。新しい健常組織が中から盛り上がっていくように修復されます。むしろ充分盛り上がる前に皮膚だけ閉じないように創内にガーゼを充填しておきます。
(人間の身体は見事なもので、条件がそろわない間は健常組織はなかなか出てきませんが、創環境が整いだすと一気に治りだします)
こうなるとちょっとした手術ですし、少なくとも一週間は通院する必要があります。
ここまでする「目的」は?
「再発予防」です。
官僚が国民のために仕事ができる「仕組み」を作る必要があると思うのです。
今はそうではない?たぶん違うのでは・・・
戦後財閥や地主は解体しましたが、官僚組織は?
となると、官僚組織のコンセプトは大久保利通のまま・・・
竜馬でも無理だったのですから大久保に対抗する人物の登場に期待するのは夢物語でしょう。
例えば、C型肝炎のリストが出てきたら、それを隠すより報告する方が「得」になるシステムにするわけです。人間「徳」だけでは厳しいのでは・・・
今までより新しくいい物に変えた人が「偉い」という価値観を官僚システムの中に・・・「変えないという良さもあるはずだ・・・」
でもこれはうる覚えですが、私達の体を構成している「水」はかなり短いスパン(一週間だったでしょうか?)で入れ替わるという話を聞いたことがあります。つまり、私たち自身が一週間前とまったく同じ存在ではないということになります・・・全く変わらないということの方が不自然なのでは・・・
—-
あとはマスコミ・・・
最近朝青龍の事報道しませんが、もう目を逸らす元が片付いた?


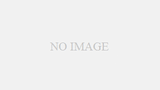
コメント