「梯子をはずされても・・・」でアメリカの世界を多極化するという戦略について触れました。昨今の6カ国協議の進み方やF-22戦闘機の輸出禁止等の動きも背景に多極化があるとすると理解できます。
しかし、今回の参院選でその対応は論じられていませんでした。
マスコミがこの観点で書いているものも、少なくとも私は見ません。
しかし、これに対する対応は歴史的な選択になるはずです。アジアの事はアジアでやってくれ、とアメリカがするとき日本は・・・
それに対してどう考えればいいのか導いてくれる論文を新聞で見る事が出来ました。ハーバード大教授である入江昭先生が寄稿した「現論」がそれです。
先生は、まず日中韓のGDPは「購買力で換算した数字」ではアメリカのそれを超え、東アジアへの関心が高まっているとしています。その上でこの地域におけるナショナリズムの高まりや国益の対立を緩和する事は急務であると欧米からも指摘されていると紹介しています。
先生は「グローバル化を促進し、国家関係の緊張を緩和するには地域主義的な思考や機構が今後きわめて重要になる。」としています。
私にはこのリージョナル(地域)な共同体の形成という発想はほとんどありませんでした。しかし、地勢学的にもそしてすでに成功しているEUをみても、キーワードは「地域」であることを踏まえたいと思います。
しかし、それはこの地域(東アジア)でも出来るのでしょうか・・・
この数十年の間、政治的にも社会的にもこの3国は様変わりしており、先生は悲観する必要はないとしています。
それには避けて通れない過去の共有は、この地域の共同体形成の過程として位置付けられるべきでしょう。


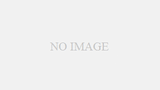
コメント